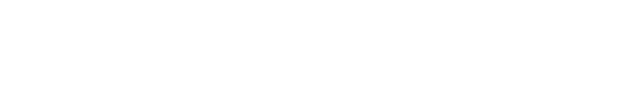冷え性と漢方
[2024.12.05]
寒くくなり、冷え性を主訴に受診する方がありました。冷えと漢方についても考えてみたいと思います。漢方が強い分野の一つであります。漢方以外には冷え性の治療薬はビタミンEくらいしかありません。当帰芍薬散、五積散、真武湯など冷えの漢方を院内処方にて常備しております。
足であったり、腰であったり、おなかであったり、指先であったり、本人の自覚で冷感を感じている状態。冷え性の定義はこうなるかと思います。実際は機能的には正常で冷えを感じても本当に体温が下がっていることは少なく、低体温症とは別の病態です。手指の末端や耳などで温度が下がることにより起こる病態が凍瘡(しもやけ)で。末梢の循環障害により発赤や腫脹があり痛みやかゆみを伴う病態です。冷え性は婦人病の代表的なものですが、体質的なものであり避けれないところもあります。冷えを避け保温することは重要ですのでまず心がけてください。レイノー減少や閉塞性動脈硬化症といった器質的な病態では漢方は不向きです。
活血作用、瘀血(悪い血がたまっている)の改善、漢方ではこのような考え方をします。たくさんの処方がありますがいくつか代表的なものを紹介します。
五積散は血行を促進して全身を温めます。冷えで腰痛を感じる、腹部の冷えを感じるといった方への処方になります。
当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)は、手足の冷えへの漢方です。しもやけにもよく使用されています。
人参養栄湯はおなか温めて、腹痛や下痢を直します。大建中湯も腹部に冷えに使用します。
もう一つの瘀血の改善目的に使用する薬剤は桃核承気湯、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散などがあります。夏でも冷える、顔がのぼせるが下半身は冷える、顔色が悪い、舌の裏の血管が怒張している、月経痛、月経不順など婦人科病をともなう、肩こりが強い、などが瘀血のサインです。